
子育ってイライラする
子育てをする中でイライラすることはあると思います。急いでいるときにふざけてみたり、用事をしているときに邪魔されたり。
イライラするのは、自分都合ですよね。
では、イライラしないために、子どもが言うことを聞けるようになればいいでしょうか?
子育てって不安になる
子育てって正解がわからず、周りの子が何かできていることで、うちの子ができないと不安になったり、焦りますよね。
幼児教室に通っている子がいる。うちも通わせないといけないだろうか。。。
自分が至らないせいで、子どもに何か悪影響が?とか。
イライラと不安の正体
上記したイライラと不安は、子ども起因でしたか?
実はとても自分本意なんです。子育てって、自分が子どもを育てなければいけないと言う前提がありますよね。
でも、実は親にできることは子どもの自主性に合わせることくらいです。
子どもをコントロールしようとするから、大変
子どもの向いているベクトルと違う方向に向けたり、抑えようとするから大変なのです。
「人は変えられない」と認識されていますか?
夫や姑、上司・部下を変えようとして、トラブルになる人いますよね。
認識していても、自分の子どもだとそう思えなかったり・・・
そうは言っても、「私の言ったことで変わった人もいるよ!」と言う反論があるかもしれません。それは、「言うことを聞いた」ではありません。その人に言葉が届いて、本人の経験や意志と結びつき、本人が納得し、そうしたいから、変わったのです。
言葉はきっかけは作れると思います。
やる気スイッチを押せる?
やる気スイッチを押すCMがありましたね。親は探すことができても、結局最後押すのは、本人です。
探す作業は一緒にしてあげられるといいですね。
外から変える、内側から変わる
人が変わると言うのは、外から変えることではありません。その人の内側からその人発動で変わるのです。
外側から変えることの一つに、賞罰があります。賞罰はその時の行動が変わることがありますが、その人自身は変わっていません。
例えば、交通違反をして捕まります。罰があります。そのことでその人は変わるでしょうか?
反省する気持ちになったり、本人が困れば、態度を変えることができるでしょう(これも態度・行動は変わりますが、本人が変わったわけではありません)。別の交通違反はするかもしれないし、罰則のない違うことではルールを守れないかもしれません。
また、「運が悪かった」「なんで自分だけ」などと捉えれば、また同じ交通違反を起こすでしょう。
子育てで、親ができることとできないこと
上の、賞罰の例でもわかるように、賞罰に人を変える力はありません。ここでもきっかけの一つになることはあります。ですが、基本的にはその人の1行動を制限・促進することができるだけです。
賞罰はともに、過激になる傾向があるので、注意も必要です。
お勉強をさせるために、何かを買ってあげる。同じ価値のもので継続はできません。
できなければ、罰を与える。最初は注意で済んだものが、罵倒になり、手を出すなんてことにも。。。
本人起因の動機がなければ何事もうまくいきません。
何より、親にできることとできないことがあることを認識しましょう。
親が子どもを理想の形にすることは、エゴです。
環境や習慣は行動に影響がある
例えば、子どもが悪い言葉遣いをする。親は使っていませんか?親が日常的に使っていて、子どもに使うなと言うのは、難しいです。
そう言う言葉を聞いたことがなければ、そもそも使いようがないです。
「保育所で覚えてきて・・・」と言う人がいますが、家で使わなければそのうち収まります。どうしても嫌なら、環境を変えるしかありません。けれども、子どもへの影響を全て排除することはできません。
「類は友を呼ぶ」と言います。時々「悪い友達と付き合って悪くなった」と言う親御さんがいますが、悪い子と友達になる時点で、その子自身同じような状態なのです。全く異なる性質なら引き合わないですよね。認識しましょう。お子さんをよく見てください。
お菓子を家にたくさん置いて、日常的に食べている親が、子どもに、おやつを食べさせないようにするのは難しいですよね。
TVが常時ついているのに、「TVを見ないで勉強しなさい」は難しいのは当たり前です。
環境や親の習慣を見直すことは大切です。今習慣づいてしまっているものは、時間がかかります。でも習慣です。慣れるまでやるしかありません。
したければする
結論は単純で、子どももしたいこと、楽しいことならします。とはいえ、例えば「朝の支度を、早くする」この動機付けは、難しいですよね。
早くいきたい子は、簡単です。進んでしてくれます。
小さい子は、とにかく楽しめるようにするのがオススメです。
競争してあげたり、数を数えたり、好きな曲が終わるまでとリミットを設け「できるかな?」と声をかけたり。
楽しければ、「ママ競争しよう」と本人が言ってきます。
「できるか?」これは子どもが自分の力を知ることです。やってみたいと言う好奇心を持てることはとても大切です。持てない子はなぜ、しようとしないのかよく見てあげてください。「できること」は本人の自信につながり次のチャレンジにもつながります。「やればできる」と知ることは本人の次の新たな行動の動機付けにもなります。
賞罰は安易で、影響力は低い
外側から与える賞罰は、たいした効果がないです。「早くしろ!」と怒ったところで、泣いてしまえば時間は余計にかかります。
そして「早くしろ!」と怒ると恐怖で動く。それが望みですか?
ご褒美も行動への負のベクトルを上回るものが必要です。
簡単にできますが、賞罰で動くことは何も学べていません。
まとめ
子どもの表面だけ見て、表面に手を出してはいけません。
行動を変えさせたい、と思うことはよくあります。けれど、本人にその気がなければ動きません。
とにかく話し合いをしましょう。納得できれば動けます。
2020年4月現在、学校も休みで、ダラダラしがちな子どもに毎日イライラを感じ、このままではいけないのでは?と不安にも思います。
そう思う中でも、できるだけ、イライラや不安に負けないよう、子どもと向き合う努力をしています。
子育てにおいても、「お互いを理解」することはとても重要です。できるだけ、効率よく、お互いに気持ちよく過ごしたいと思います。
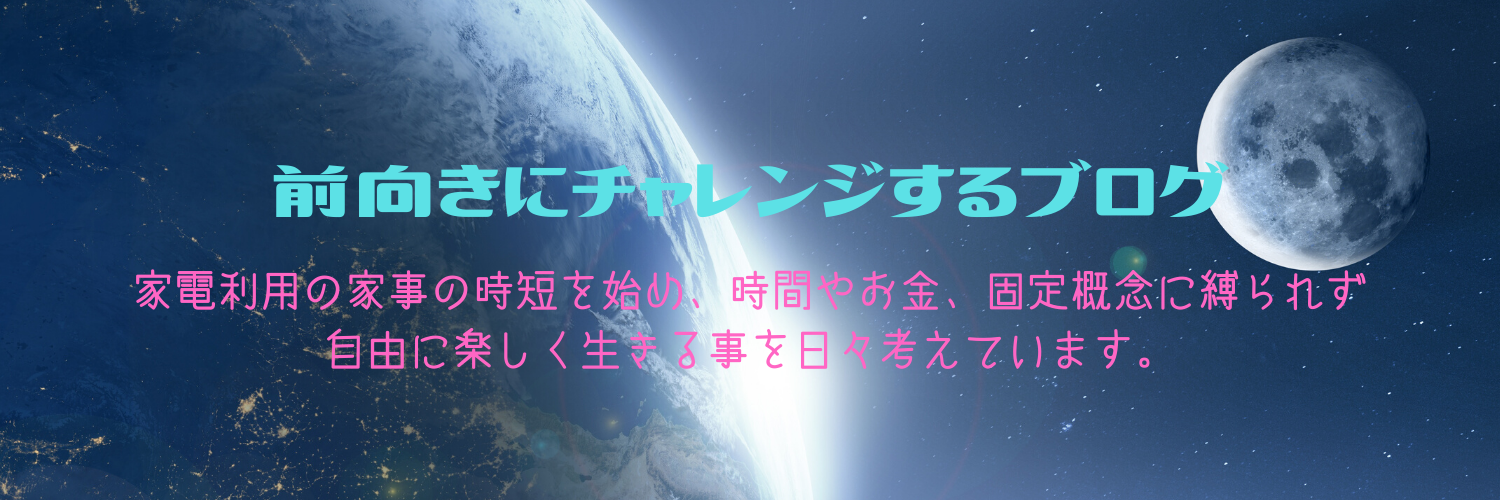




コメント